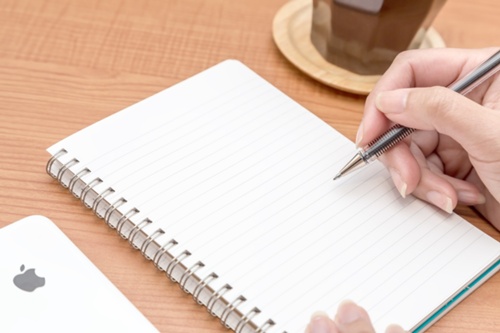【英語】大学入試のための教養指導、実践中
こんにちは。広島市で四技能型・英検対策専門の英語塾「スクール今西」を運営しております今西一太です。
先日、
という記事を書きました。簡単に要約すると、難関大学は英語力だけでなく受験生の教養や知的な関心なども測っているので、英語力だけを身につければいいという話ではない、という内容です。
そこから改めて、学生には英語力だけでなく、幅広い教養を身につけてもらう必要があると強く感じています。
そこで現在は授業の中に 「教養を身につけるためのコーナー」 を設け、毎回5〜10分程度、英語圏の教養人の書いた文章をより深く理解するための知識を紹介しています。
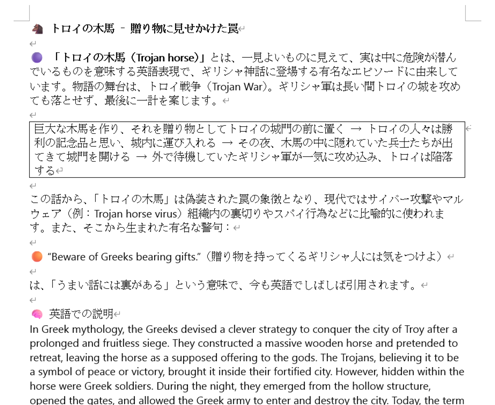
これまでの授業では、次のようなテーマを取り上げてきました。
🎭 シェイクスピア『ロミオとジュリエット』:"Wherefore art thou Romeo?" の意味
🧠 デカルト:“Cogito, ergo sum(我思う、ゆえに我あり)”
🌍 フランス語圏の広がりと植民地支配の歴史
🪙 ネルソン・マンデラとアパルトヘイト:語源と人種隔離政策
🔭 コペルニクス的転回(地動説)と世界観の変化
🐴 トロイの木馬:「うまい話には裏がある」という教訓
💭 フロイトの夢分析:夢は無意識の象徴
🪒 オッカムの剃刀:仮説はシンプルなものがよい
🧬 ダーウィンの進化論:自然選択、適者生存、共通祖先
🌟 ホラティウスの“Carpe diem”:「今を生きよ」
🏙 ブリュッセル:ベルギーの首都でありEUの象徴都市
🕍 テルアビブ:中東のシリコンバレーと呼ばれる現代都市
🕊 ガンディーとアンベードカル:カースト制度をめぐる思想的対立
これらは私のような研究者・語学教師の立場からすると「ごく基本的な常識」に見える内容です。しかし実際には、トップ進学校の高校生でも知らないものが少なくなく、そのギャップに驚かされることがあります。
大学の入試を担当する先生方は研究者であり、多くは博士号を持っています。その目線からすると、背景知識が欠けていると「英文を十分に理解できていない」と判断される可能性があります。
たとえば「ブリュッセル」と聞いてすぐに「ベルギーの首都でありEUの中心都市」と思い浮かばない場合、単なる知識不足以上に「文章の背景を読み取れていない」と受け取られてしまう危険があるのです。英語力そのものが高くても、「もう一歩踏み込んだ読解ができていない」と評価されることもあり得ます。
例えば以下のような文章は大学入試レベルでは十分出題される可能性があります。このとき、「トロイの木馬」が何であるか、その歴史的背景とともに知っているかどうかでこの英文がきちんと理解できるかが全く変わってくることは容易に想像がつくでしょう。
現在の学校教育は「首都暗記」や「古典的な逸話」を重視しない方向にシフトしています。環境問題や現代社会的なテーマが優先されるためです。これは大切な学び方ではありますが、大学受験の観点からすると必ずしも最適ではありません。
入試問題は研究者である大学教師が作るため、「研究者にとっては常識」レベルの教養が前提になっていることが多いのです。したがって、学校教育だけに依存していると、必要な背景知識が不足するリスクがあります。
私は今後も授業の中で、この「ワンポイント教養」の時間を継続していきたいと考えています。受験生にとってそれは知識の詰め込みではなく、視野を広げ、思考を深めるきっかけになるからです。
結果的に、それが英文をより深く読み解く力となり、大学入試で他の受験生との差を生む「武器」となるはずです。そして将来、世界とつながって学び働くときにも、必ず役立つ土台になるでしょう。
英語学院TOPページ
講師プロフィール
中学生・高校生の英語指導
大人の英語指導
大学受験の英語指導
入会までの流れとよくあるご質問
生徒・保護者様の声
英語学院授業料
スクール今西 Facebook