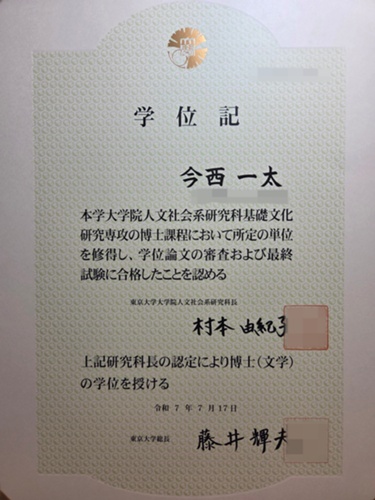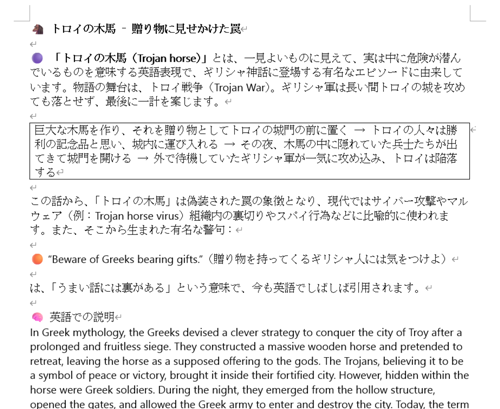【英語】英検準1級・意見英作文の模範解答が変わった!
こんにちは、広島市の四技能型・英検対策の英語塾、スクール今西の今西一太と申します。
英検準1級の意見英作文は、ここ1年(2024年~2025年)で模範解答の「序論」部分(第一段落)が明確に変化してきているのをご存じでしょうか?とくに2024年度第2回以降は、それ以前とは異なる「構成」や「導入の仕方」が見られます。

この記事では、2023年度第3回から2025年度第1回までの5つの模範解答の序論を比較しながら、その変化のポイントを解説します。
英検準1級の英作文をより高得点で突破したい中高生や、指導者の方にとっても有益な気づきになると思います。
結論から述べると、
ということが言えます。詳しくは以下をご覧ください。
The government should make a greater effort to encourage young people to vote in elections. I will explain from the perspectives of taxes and social responsibility.
→ いきなり「政府は投票率を増やすための努力をすべき」と結論を述べて、その後に理由を予告するだけのシンプルな構成です。これは以前までの準1級の模範解答と同じです。
The government should encourage the use of vacant land in urban areas for farming. The reasons for this are related to costs and population.
→ こちらも旧来型。「導入」なしで結論から始まるスタイルが継続しています。
When it comes to searching for a job, a high salary should be the top priority. It offers many benefits, including better career opportunities and an improved quality of life.
→ “When it comes to~” というトピック提示型の導入が登場しました。文の構造がやや複雑になってきた印象です。
Although dangerous animals may be attractive as pets, there are too many risks. People should be banned from keeping dangerous animals as pets for reasons related to safety and animal welfare.
→ 「譲歩構文(Although~)でテーマの導入 → 主張へ」という、より英語らしい流れに明確な変化が見られます。
As the global population swells, the question of whether governments should work together to increase global food production is important. I believe international cooperation is needed to address limited land space and to effectively create new technology.
→ 「背景提示 → 結論」の順に述べる「二文構成の序論」が完成。アカデミックな英作文の基本型に近づいています。
時系列で見てわかるように、2024年度第2回から次第に「導入(introduction)」→「立場の表明(thesis)」という構成が模範解答に反映され始めています。
変化のポイントをまとめると:
| 年度 | 導入の有無 | 結論提示の位置 | 序論の構造 |
| 2023-3 | なし | 冒頭 | 結論のみ |
| 2024-1 | なし | 冒頭 | 結論のみ |
| 2024-2 | あり(トピック導入) | 冒頭 | トピック紹介+結論 |
| 2024-3 | あり(譲歩構文) | 2文目 | 導入+主張 |
| 2025-1 | あり(背景説明) | 2文目 | 背景提示+主張 |
このように、旧型の「いきなり主張スタイル」から、「背景情報の提示のあとに自分の主張を述べる」という英語論文の基本構造へと移行しているのがわかります。
英検はCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)との整合性を重視しています。英検準1級が該当するとされるB2程度レベルでは、「構成の明確さ」や「論理的な展開」が評価基準に含まれているため、模範解答もそれに対応する形になっていると考えられます。
国内でも、英語エッセイの基本である「導入→主張→理由→結論」の4段構成が、学校教育などで重視されるようになってきました。模範解答もそれに呼応して変化している可能性があります。
2025年度から新たに導入された「準2級プラス」は、準2級と2級の間の“橋渡し”のような位置づけの試験です。この新設によって、2級と準1級の難易度が上がり、準1級が本来意図されていたB2レベルにより忠実に近づいたとも言えます。
つまり、以前は「B1寄りのB2」だった準1級が、現在では「C1寄りのB2」に向かって引き上げられている──その結果として、英作文の解答もより高度で整った構成が求められるようになってきたと考えることができます。
これから受験する人は、「冒頭でいきなり主張」よりも「一文でテーマを紹介してから主張に入る」構成を意識しましょう。
指導者も、従来の「型どおりのテンプレ」だけでなく、英語圏のエッセイの基本構造に近い指導を取り入れることで、より高得点を目指してもらえる可能性があります。
かつての模範解答の序論(第一段落)は、「短く」「簡単に」「すぐ主張を述べる」ものでしたが、2024年から模範解答が“英語らしく”進化し始めています。
第1段落は単純に結論を述べるだけでなく、「背景情報の提示→自分の結論の提示」の流れを意識したほうが、高評価につながる可能性があります。
たった数行の序論にも、英語圏の論理構成の考え方が反映され始めている──その変化に気づいた今こそ、英作文の学び方・教え方をアップデートするチャンスかもしれません。
今回の記事で紹介したような「導入→結論」という構成は、私自身、以前から英作文講座で指導していたものです。上にも記載した下記の記事でも詳しく述べていますが、英作文の序論は本来「general to specific」、すなわち一般的な導入から徐々に話題を絞っていき、最後に主張を述べるという流れが自然であり、英語圏の論文構成としても基本です。
ただし、これまでは英検準1級の模範解答を見ても、「結論だけをいきなり述べる」という構成が一般的で、試験上それで十分とされてきました。そのため、指導の現場では「本来は導入から書くべきだけど、英検ではこのぐらいでOK」という妥協的な教え方をせざるを得ない場面もありました。
ところが、今回見てきたように、模範解答そのものが2024年度第2回以降、少しずつ“本来の英語らしい構成”に近づいてきています。これは指導者にとっても非常にありがたい変化であり、今後はより自然な構成をそのまま教えられるようになると感じています。
英語学院ブログ記事 ジャンル別まとめ
大学レベルの英作文指導を中学生・高校生に
日本人が英作文でよく使うけど実は不自然な表現3つ
これだけは必ず守るべき英作文の構成 基本中の基本
文法的には正しいけど英作文では避けるべき4種類の表現(英作文と口語表現)
英語学院TOPページ
講師プロフィール
中学生・高校生の英語指導
大人の英語指導
大学受験の英語指導
入会までの流れとよくあるご質問
生徒・保護者様の声
英語学院授業料
スクール今西 Facebook